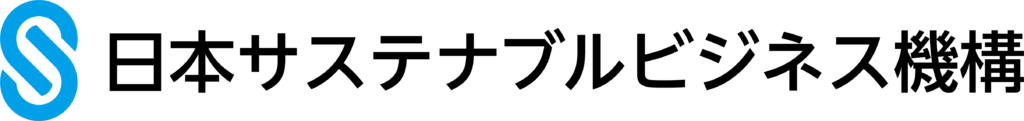2025.10.24 / お知らせ
10月15日地域と未来をつなぐSDGs実践と学びのフォーラムを開催しました
1. 開催概要
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 地域と未来をつなぐSDGs実践と学びのフォーラム |
| 主催 | 一般社団法人 日本サステナブルビジネス機構 (JSBO) |
| 共催 | 豊田市 |
| 日時 | 2025年10月15日(水)10:00 – 12:00 |
| 場所 | 名鉄トヨタホテル(愛知県豊田市)国際首長フォーラム内 |
| 目的 | SDGsやサステナブルに関する大人たちの活動と、学生・現場の視点とのギャップを共有し、学びの場とする。 |
プログラム
| 時間 | 内容 | 登壇者(予定含む) |
| 10:00-10:05 | 開会 | JSBO |
| 10:05-10:25 | Beyond SDGsを地域の力で | 蟹江 憲史 JSBO理事長 |
| 10:25-10:45 | 地域共生と世界をつなぐ豊田市SDGsの活動 | 太田 稔彦 豊田市長 |
| 10:45-11:05 | 豊田KOSENのSDGs実践活動〜地域課題解決学生プロジェクト〜 | 松本 嘉孝 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授/専攻科長 |
| 11:05-11:25 | 豊田鉄工(株)とトヨテツの森の活動について | 水野 幸太 豊田鉄工株式会社 プラント環境技術部 環境企画室 担当員 、 土屋 浩二 豊田鉄工株式会社 経営企画部 経営企画室 室長 (豊田市SDGsゴールド認証企業) |
| 11:25-11:45 | 加山興業の挑戦と地域の巻き込み方 | 加山 順一郎 加山興業株式会社 代表取締役 (JSBOブロンズ認証予定) |
| 11:45-11:55 | QAトークセッション:未来を創る学生×地域SDGs | 学生、企業、参加者全体+モデレーター |
| 11:55-12:00 | まとめ・閉会の挨拶 | JSBO事務局 |
| 12:00- | 名刺交換・情報交換会 |
2. 講演・発表の要点
2-1. Beyond SDGsを地域の力で(JSBO理事長 蟹江 憲史氏)
- SDGsの重要性: 経済成長だけでなく、社会・環境を含めた成長を考える必要がある。「Beyond GDP」の議論が進み、ウェルビーイングや幸福度といった指標の重要性が出てきている。
- 地球規模の課題: 経済成長(グローバル化)の一方で、地球システムは悪化し、気候変動や格差などの歪みが生じている。これを変えるには、トランスフォーメーション(変革)が必要。
- SDGsの現状: 目標だけの体系で、細かいルールはない。現状、18%の目標がこのままいけば達成可能、35%程度はなんとか達成可能だが、残りの65%は相当な努力が必要。
- 達成を阻む3つの危機: パンデミック、戦争(紛争)、気候変動。
- 変革への道筋:
- 企業が「SDGsを推進する」ためにやるではなく「経営課題からSDGsにリーチする」ことが推進のカギ
- まずは「見える化」(測ること)が大事。
- 実験的な取り組みから始め、仲間を広げて大きな力とし、経済的な合理性を生む。
- JSBOの取り組み: 社会がSDGsに対しそれぞれの活動を推進する中、JSBOは企業がSDGsに取り組んでいることを可視化し、第三者が認める仕組み(サステナブルビジネス認証制度:シルバー/ゴールド/ブロンズ)を提供。SDGsの目標を企業活動に落とし込み、測れるようにしている。
- 未来への展望: SDGsの推進は2030年以降にもつながり、ウェルビーイングといった新たな概念も加わりながら、未来の豊かな社会の基礎となる。
2-2. 地域共生と世界をつなぐ豊田市のSDGsの活動(豊田市長 太田 稔彦氏)
- 豊田市の特徴: 愛知県の約20%を占める地域。トヨタ自動車の本社があり製造品出荷額は全国の都道府県2位(静岡県)を上回る。一方で地域の7割が森林であり、「日本の縮図」とも言われる。
- 国際的な取り組み: 2009年の環境モデル都市認定以降、国連との連携を深め、2015年には持続可能な都市に関するハイレベルシンポジウムを、今年は国際首長フォーラムを開催。
- 実績: 日本経済新聞社のSDGs先進度調査で全国1位の評価。「日常生活」がSDGs先進と評価されるのは、逆にその取り組みが当たり前になっている証拠であり、外部目線での評価が重要と考えている。
- 地域共生:
- 「共同」の概念: 一般的な「協力して働く」ではなく、「共に働く」を重視。行政がやることに市民が協力するだけでなく、市民だけで課題解決を行う仕組みが重要。
- 具体的な仕組み: わくわく事業(住民が税金の一部を使い道を決める)、地域課題解決事業(地域が提案し、市が関わって解決)。
- プラットフォーム: とよたSDGsパートナー(企業が社会課題解決と新ビジネス創出)、おいでん・さんそんセンター(都市部と山間部の連携)、豊田市つながるくらし社会実証推進協議会(企業・研究者・金融機関等が課題解決を協議)。
- 企業連携: 豊田商工会議所、豊田信用金庫と連携し、豊田市SDGs認証制度を行っている。認証企業には入札時のポイント加算などのインセンティブもリンクさせようとしているが、実際には社会的認知度という「認証そのもの」に価値を見出す企業が多い。
2-3. 豊田KOSENのSDGs実践活動(豊田高専 松本 嘉孝氏)
- 高専の役割: 15歳から20歳までの学生を対象とし、高レベルな工学的知識・技能を身につけさせる。近年はアントレプレナーシップ教育、国際化などにも注力。
- 工学とSDGs: 工学は「物を作る学問」から「持続可能な未来を設計する学問」へと進化する必要がある。
- 主な活動(地域との連携):
- 地域活性化: 中山間地域の里山地区で小学生を招いた工学イベントを開催。若者が地域の課題解決に関わる場を提供(SDGs 4,11)。
- 民間企業との交流: 建設会社と連携し「夢の新住宅・共創プロジェクト」を実施。学生が建築設計士と協働し、実際に建築・販売(SDGs 8,11,17)。
- 国際交流: 海外学生を招き「未来のスマートシティを作る」をテーマに議論(SDGs 4,11)。
- 行政との連携:
- 上下水道局と連携し、マンホール蓋のアップサイクルや、水道水に関する研究・啓発活動を実施(SDGs 11,12)。
- 他高専との連携: 鳥羽商船高専と連携し、大量廃棄される牡蠣殻を建材へアップサイクルする研究。CO2吸収量などを科学的に定量化・見える化(SDGs 9,12,13,14)。
- 今後の課題(教育におけるSDGs):
- 教育におけるSDGsの可視化:学んでいることがSDGsとどう関係しているかを教員・学生ともに理解できていない部分がある。
- 工学と倫理(SDGs)の組み合わせ。
- 自己達成度の評価: 単位や成績ではなく、「自分が何ができたのか」という自己到達度をSDGsと絡めて測ることが求められている。
2-4. 豊田鉄工(株)とトヨテツの森の活動について(豊田鉄工 水野 幸太氏、土屋 浩二氏)
- 企業概要: 1946年創立。自動車車体骨格部品が主力。水耕栽培によるベビーリーフ、パーソナルモビリティ「コモビ」など新規事業も展開。豊田市SDGsゴールド認証を取得。
- 環境への取り組み: 脱炭素(SDGs 7,8,9,13)、循環(SDGs 6,8,9,12)、自然共生(SDGs 2,11,14,15)、マネジメント(SDGs 3,4,16,17)の4本柱。
- トヨテツの森の活動(自然共生):
- 2013年設立。東の矢作川と西の丘陵地帯を結ぶ「緑の回廊」として、生態系ネットワークの一翼を担う。
- 造成時に、元々ある樹木を残す、ビオトープを作るなど工夫。製造業での自然共生活動の先駆けとなった。
- 環境教育: 従業員家族や近隣小学校家族を招き、自然共生プログラムを毎年3回実施。生き物探しや工作を通じ、最後に「SDGs行動宣言」を親子で発表し、バッジを授与。
- 成果: 2016年の調査開始から生き物の種類や生息数が増え続け、現在は277種を確認。自然共生サイト認証を受け、OECM国際データベースに登録。
- 新たな自然共生の取り組み:
- ぬかたの森の活動: 岡崎市の額田工場敷地内の森林(7.5万m²)で間伐を実施し、健全な森林・土壌づくり、CO2吸収増加を目指す。
2-5. 加山興業の挑戦と地域の巻き込み方(加山興業 加山 順一郎氏)
- 企業概要: 1961年創業。愛知県豊川市にメインプラントを構える産業廃棄物処理業。搬入量の約80%をリサイクル(石炭代替燃料、ガラス再生など)。
- 戦略: 企業存続のためには、自社だけでなく地域住民、社会全体の理解、すべてのステークホルダーとのつながりが不可欠。
- 重要課題と取り組み:
- 適正処理・資源循環: 太陽光パネルリサイクル処理機の導入。AI画像認識を利用した選別ロボットを開発・導入。廃おむつのリサイクルに向けたコンソーシアムへの参画。
- 地球共生: 2021年にラオスに現地法人を設立。現地の埋め立て廃棄物からプラスチックを分別・破砕し、セメント工場で石炭代替燃料として利用。途上国の環境改善に貢献。
- 環境共生: 廃棄物処理場のすぐ裏庭でKAYAMAみつばちプロジェクトを運営。「ゴミを扱う会社でもミツバチが飼えるほど綺麗な環境」をPR。
- 環境教育・普及啓発:
- 小学校4年生を対象に環境授業を毎年継続的に実施(豊川市内約20校)。
- 地域イベントで廃材を使ったリサイクルワークショップを開催し、市民の分別意識向上を促進。
- 地域高校生と連携し、ミツバチ関連商品のラベル制作やSNS発信を共同で実施。
- 取り組みの障壁と成果:
- 社内の理解: 初期は「何のためになるの?」「お金に繋がるの?」という声があったが、経営層の強い意思と、メンバーによる全社員への継続的な重要性の伝達により克服。
- アウトプット: 環境授業を受けた学生が入社をノックしたり、地域の大人たちからの理解が得られた。企業側も学生から学びを得ている。
- 外部評価: サステナビリティレポートの発行、愛知環境賞銀賞など受賞。メディア露出が増加。
- 企業の価値: 事業価値(収益)+事業外の価値(信頼、共感)が重要。
3. QAトークセッションの要点(未来を創る学生×地域SDGs)
- テーマ: 学生の就職活動におけるSDGs意識と、企業・行政の連携について。
- 学生の意識:
- 学生の90%以上が、企業のSDGsやサステナブルな取り組みを気にして就職先を考えている。
- (高専の松本先生より)今の学生は小中学校からSDGsを学んでおり、「当たり前のこと」として認識している。大人たちが「ファッション」や「企業価値向上策」として捉えているのとは根本的に意識が異なり、企業側はそこをキャッチする必要がある。
- 豊田市の対応(行政):
- SDGs認証制度のほかにも、「働く人が生き生きと輝く事業所を表彰する制度」など、さまざまな切り口で認証制度を設けている。
- 行政の役割は、企業が行う多様な良い取り組みを「顕在化」「可視化」し、学生やリクルート側が判断材料として利用できるようにする中継ぎである。
- 加山工業の成果(企業):
- 継続的な環境教育・イベントを続けた結果、10年前に環境授業を受けた子どもが入社をノックした事例がある。
- 地域のイベントへの積極的な参加により、子どもの親など地域住民の理解や共感を得られ、それが企業の採用にもつながっている。
- 学生と接することで、企業側も学生の考え方から多くの学びを得ており、双方向のアウトプットがある。
- 事業活動との両立(企業への質問):
- 豊田鉄工: 環境貢献を企業の根幹である「生産活動」と関連付け、生産活動の申請書等にSDGsの何につながるかを記入する欄を設けることで、事業活動とSDGsへの貢献を意識付ける工夫をしている。
- 加山工業: 経営層が全従業員に「この取り組みをしないと企業として生き残れない」という強い危機意識と重要性を直接伝え、時間をかけて理解を浸透させた。また、SDGsに取り組むことが「お客様に選ばれる企業」になるために必要不可欠であると説明している。
4. まとめと提言
本フォーラムは、SDGs達成に向けて、行政、教育機関、企業それぞれの立場からの具体的な実践活動と課題、そして未来を担う学生の意識が共有された「学びの場」となりました。
- SDGsは「その先」へ: 2030年がゴールではなく、ウェルビーイングといった新たな概念も取り込みながら、持続可能な未来社会の基盤として、SDGsの取り組みを継続・深化させる必要がある。
- 連携と可視化の重要性: 豊田市による多様な認証制度の整備や、JSBOによる認証制度の全国展開は、企業の良い取り組みを「可視化」し、学生や社会からの評価を受けるための重要な基盤となる。
- ローカルからグローバルへ: 豊田高専の地域課題解決プロジェクトや、加山興業のラオスでの環境改善事業のように、ローカルな活動がSDGsの目標達成に結びつき、最終的にグローバルな課題解決にも貢献する。
- 人材確保と企業価値: SDGsへの取り組みは、企業の「事業外の価値」(信頼、共感)を高め、SDGsを当たり前とする次世代の学生に選ばれる企業となるための必須条件となっている。
JSBOは今後もこの「地域と未来をつなぐ」連携をさらに強化し、サステナビリティを軸とした「3官学+サステナビリティ」の推進を通じて、より良い社会の実現に貢献していきます。